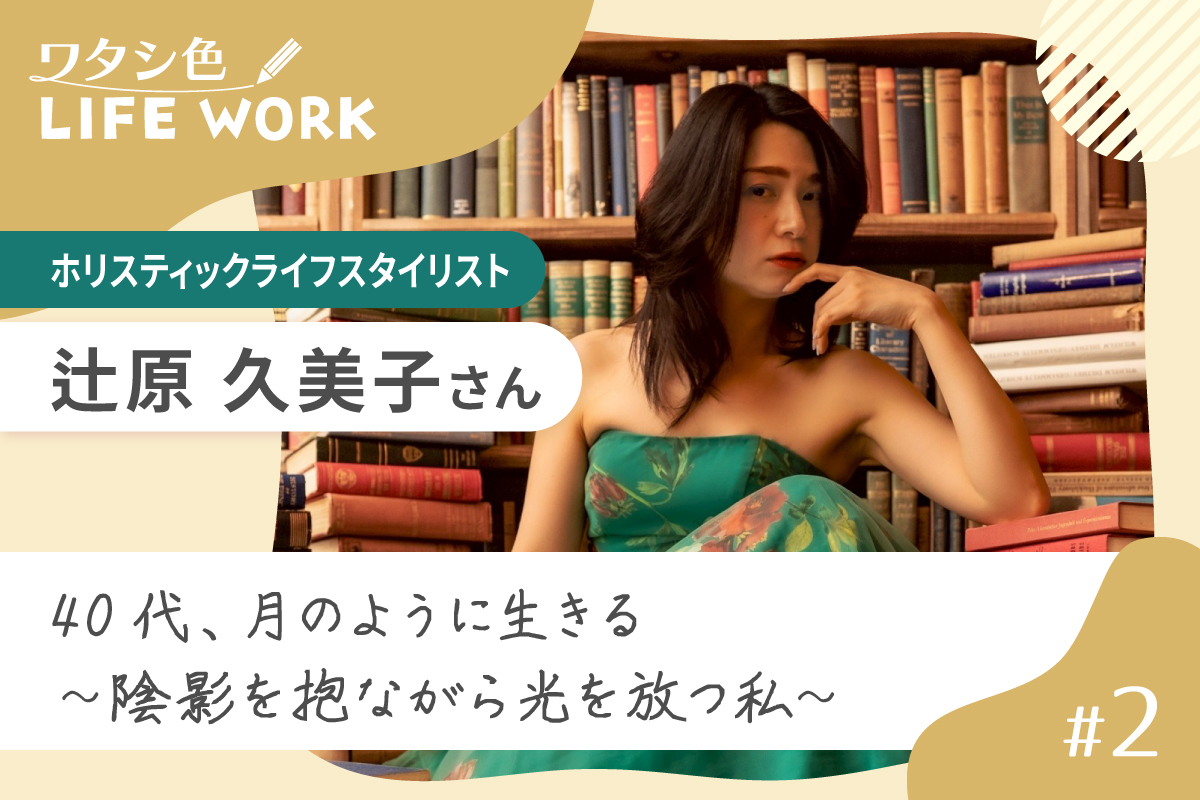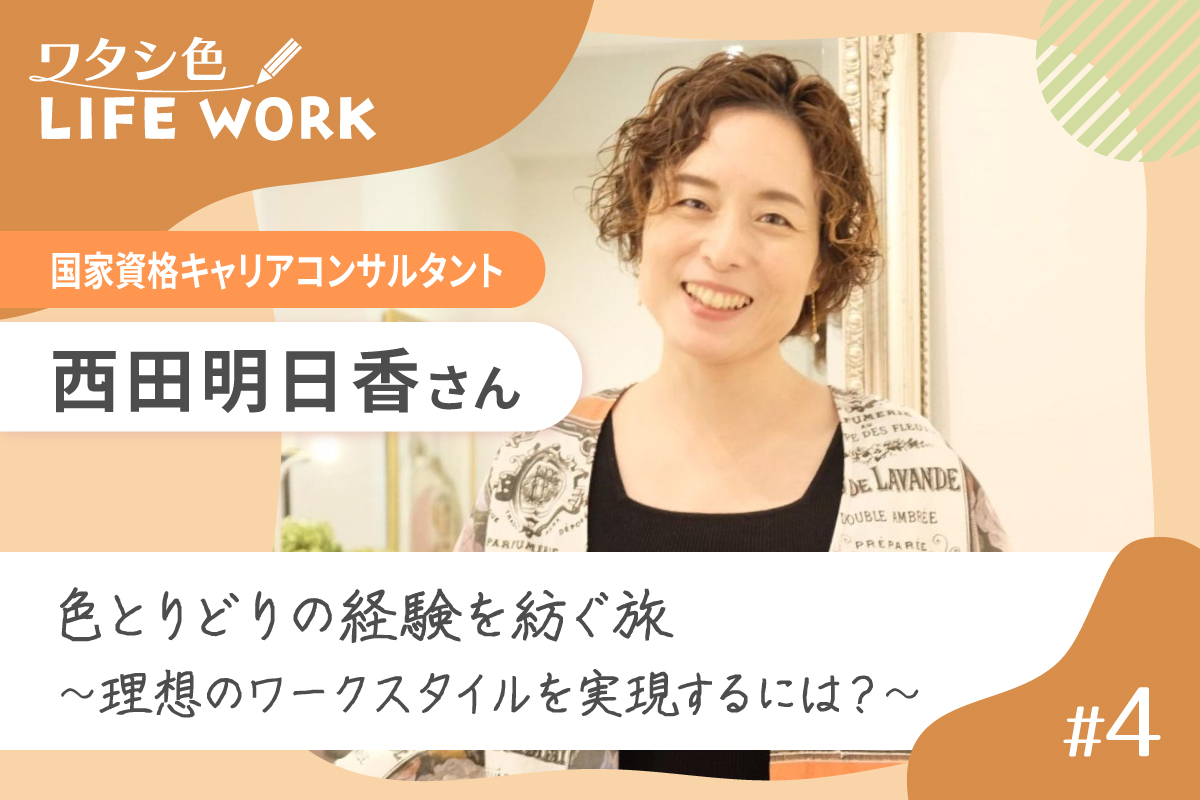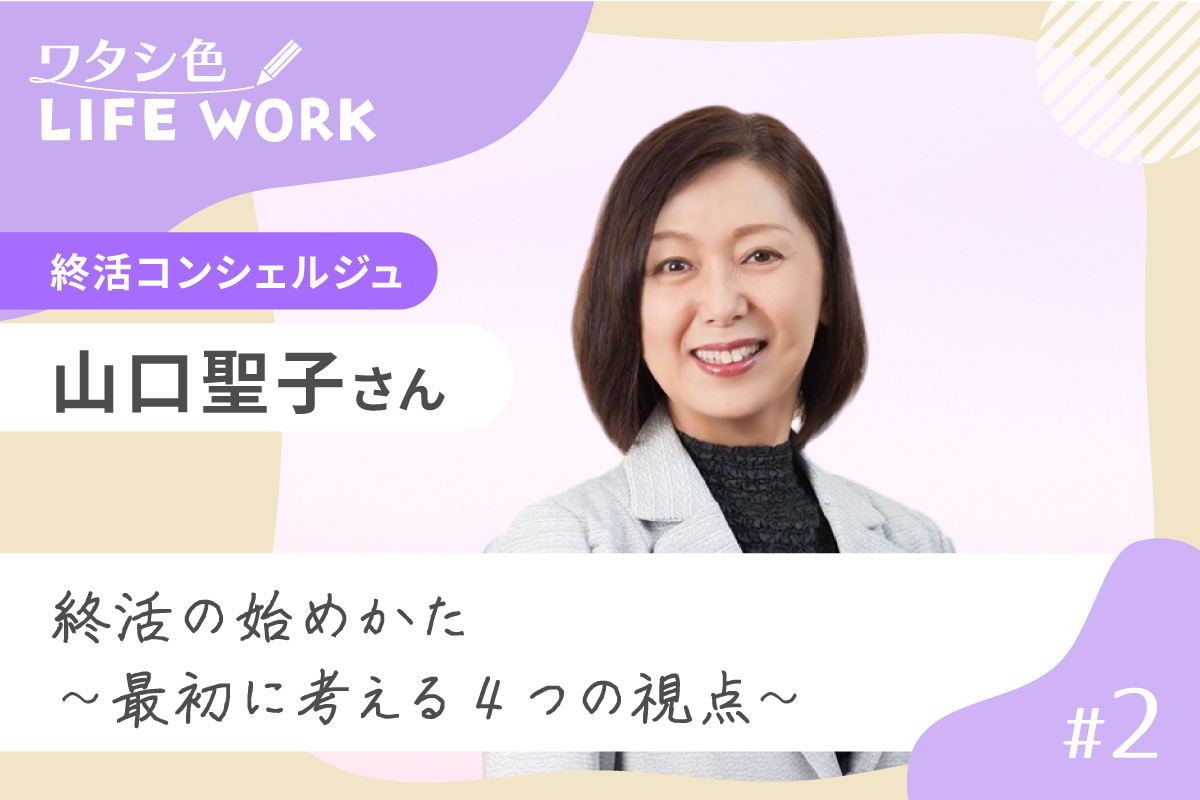
こんにちは! 終活えんとらすと の山口聖子です。
初回の前回は、私の終活との出会いとそれを伝える思いについてお伝えしました。
今回は実際に 【終活って何をしたらいいの?】 についてお話ししてみたいと思います。
前回、終活は自分が亡くなった後の準備だけではなく「今をよりよく生ききるための準備」であり、「大切な人を、事を、物を守り、思いをつなぐシナリオ作り」とお伝えしました。
「もしもの時、家族に迷惑をかけたくない」 「親に終活をしてもらいたい」と思うのは、なぜでしょう?
超高齢社会では、長生きリスクと言われるようになりました。寿命と健康寿命に差があり、その差から終焉までに辛い介護の時間が当たり前のようになってきたからです。大変な介護が終わって見送った後には休む間もなく複雑になってきている死後事務を、残された少ない身内で処理しなければならなくなりました。想像するだけで気が重くなりますね。けれど、それらは避けては通れない事実なんです。
想像できるから、あるいは、既にその大変さを経験してきたり、聞いたりしたから 「迷惑をかけたくない」 「終活をして欲しい」 という思いになるのですね。
●未来を見据えたリスク管理の第一歩
命あるものは、いつか必ずそれが尽きる時が来て、永遠に続くものではありません。
今日の元気が明日も3か月後も1年後も10年後も続くとは限りません。
逆に長生きできても高齢者の5人に1人が認知症もしくは認知症予備軍とも言われている時代です。
その時のために、準備や備えが必要だと思いませんか?
長生きリスクを見据え、寿命と健康寿命をなるべく近づけたい。
長生きリスクを見据え、財産を安心して管理したい。
長生きリスクを見据え、介護になった時のことも考えておきたい。
終焉が見えてきた時の延命はどうしますか?
その時施設や病院にいたら必ず聞かれますよ。
そして現世を卒業し、魂が彼岸へかえる時、亡骸はどこに落ちつきたいですか?
今は供養の仕方も自由で様々です。
まだまだあります。
デジタル化が進んできている昨今、パソコンやスマホに関するデータや解約はどうしますか。

さぁ、先ず初めにどんなことが出来そうですか?
寿命と健康寿命を近づけるには、健康管理のための食事や体力の維持、社会とのつながりを持つなどがありますし、転んで骨折やケガなどしないよう、室内の整理整頓も大切です。高齢者の骨折は、7~8割が室内で起こりますと、母が骨折した時の整形外科の先生がおっしゃっていました。
財産管理については、管理しやすいように口座を集約したり、民事信託(家族信託)を利用することも有効です。
介護になった時、終焉が見えてきた時の延命についての希望は、紙に書いてご家族や主治医、ケアマネージャーさん達と共有しておくことがとても大切です。
これは、介護になってからや終焉がそろそろ近づいてきてからでは、冷静に本来の希望を書いたり話し合うことは非常に難しくなります・・・というより出来なくなります。
●終活を4つの視点で整理する
終活は最初の一歩が踏み出せれば、意外とスイスイ進められるはずです。
お片づけから始めてみる。これも終活の一つです。
書店で数あるエンディングノートの中からお気に入りの1冊を見つけて書いてみる。立派な終活です。
人によっては、エンディングノート1冊を書き上げられたら、終活の7割くらいは整う人もいますよ。
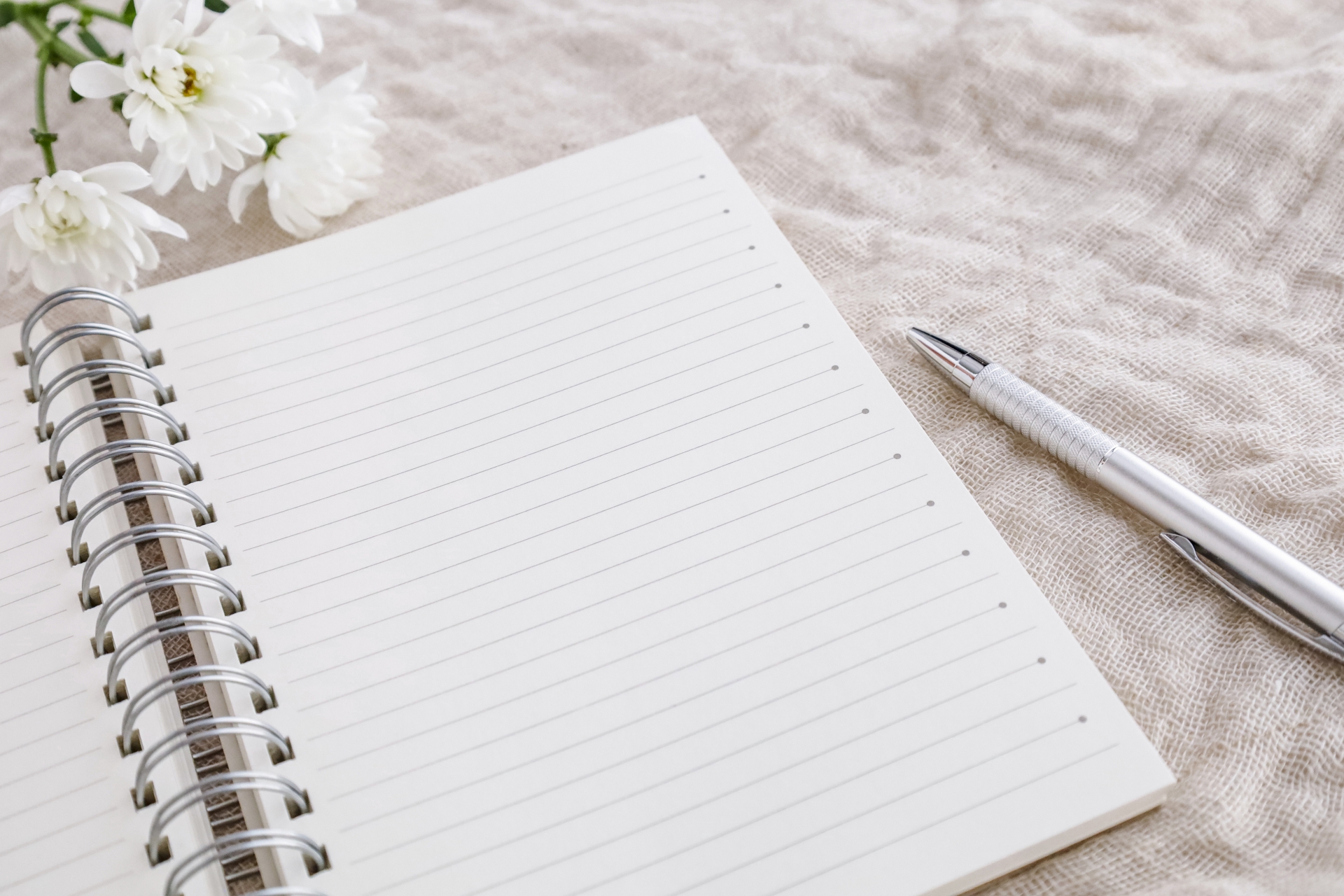
終活は多岐にわたり奥が深いのですが、わかりやすく細分化してみましょう。
1 身体のことについて(病気、介護、延命)
2 生活について(住まい、仕事、デジタル関連)
3 お金について(財産、保険、相続)
4 供養について(葬儀、お墓)
こんなことを考えながらご自身の希望やご家族に対して出来ること、協力して欲しいことを書き出してみると、必要なことが見えてくるかと思います。
次回は、多くの人が関心を寄せてくれている、認知症になってしまった時の財産管理はどうしよう!その有効な解決策をお伝えしたいと思います。

終活えんとらすと
山口聖子さん
- 終活サポート「終活えんとらすと」代表として、中高年向けの終活支援を行う。
- 両親の介護・看取りや、認知症・難病の方々のサポートを経験し、終活の大切さを実感。
- セミナーや相談を通じて「今をよりよく生きる終活」を伝え、実践をサポートしている。