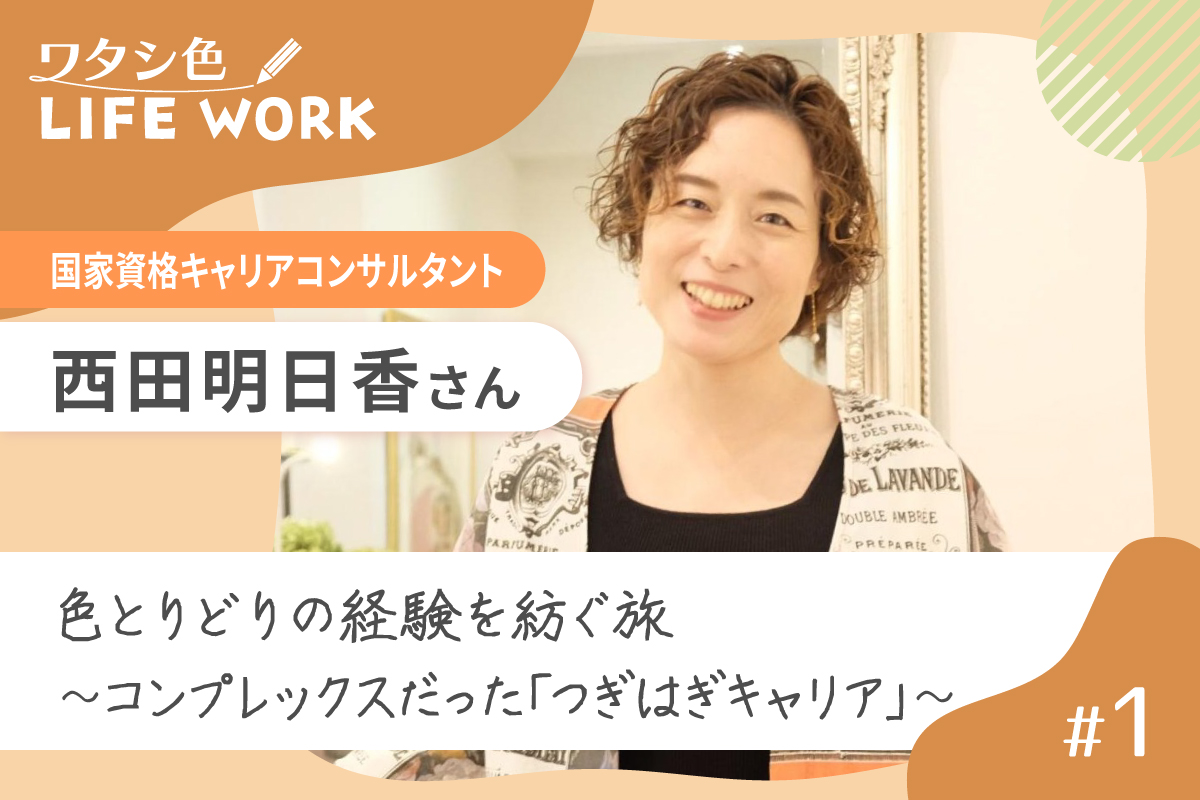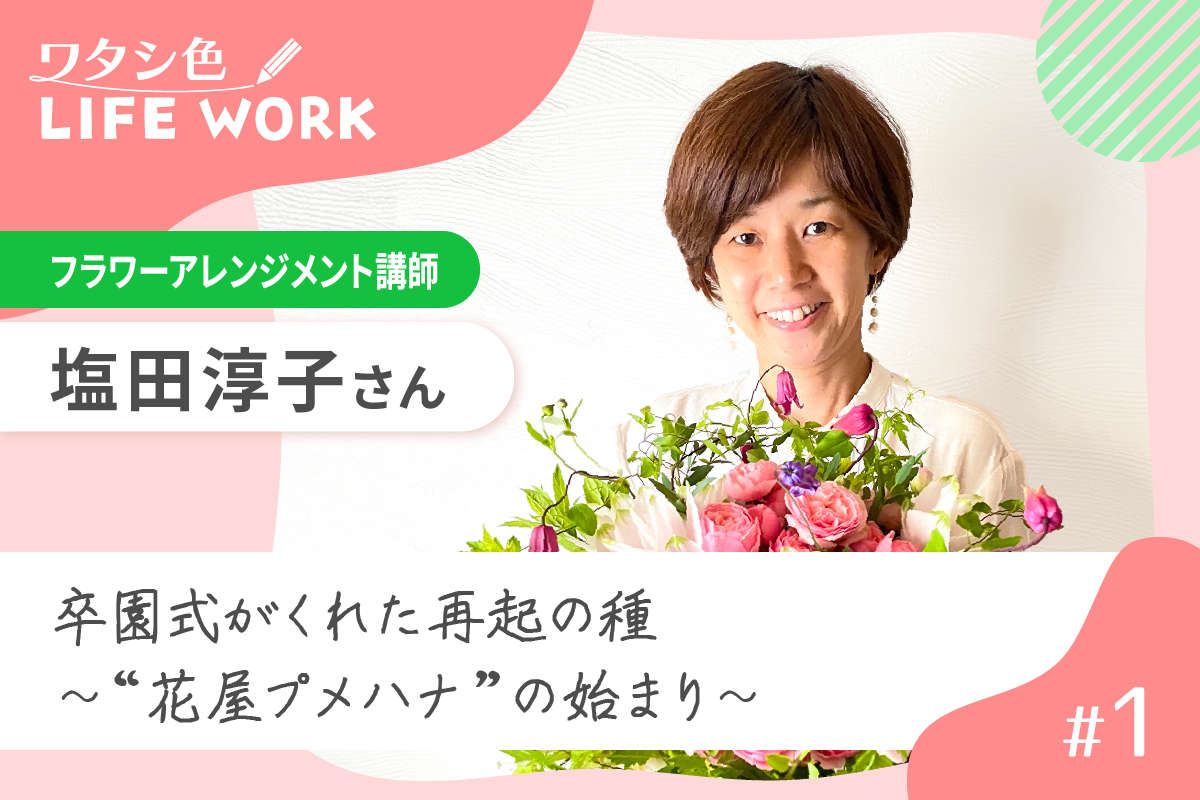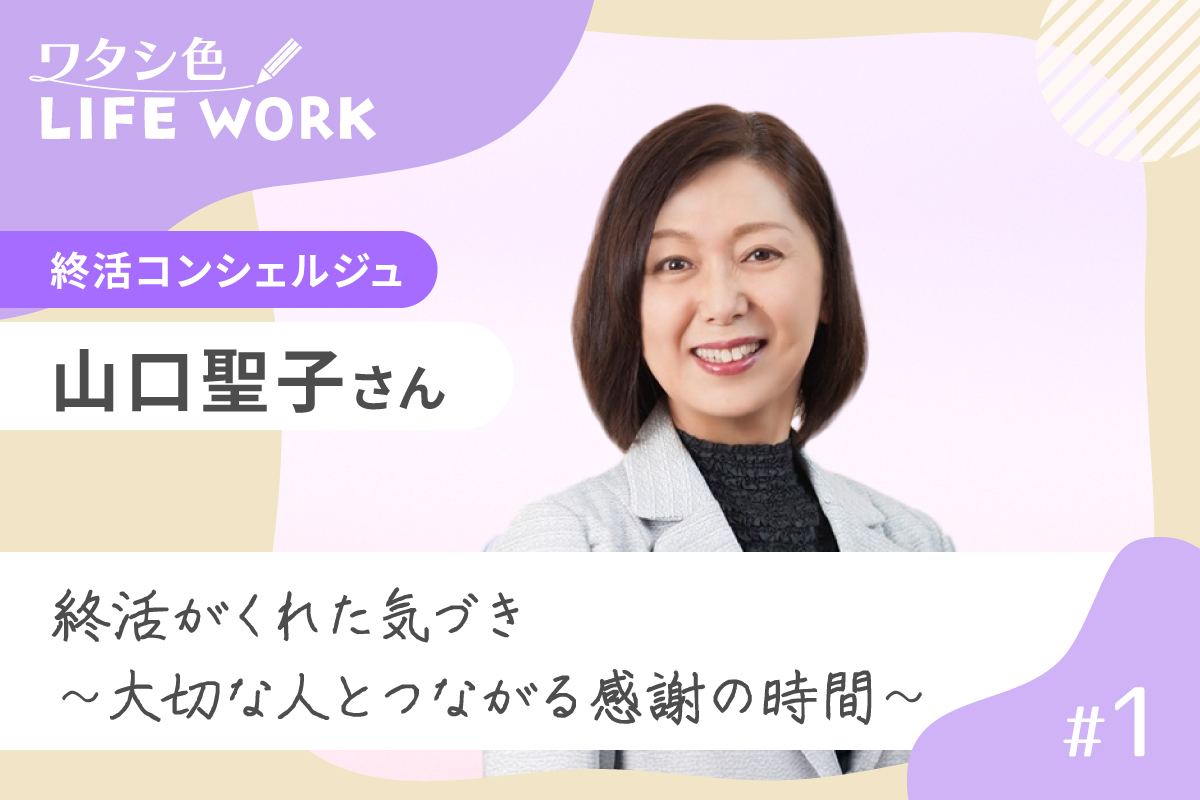
こんにちは!終活えんとらすとの山口聖子です。
突然ですが【終活】にどのようなイメージをお持ちでしょうか。
「もしもの時、家族に迷惑をかけたくない」「親に終活をしてもらいたい」そんな思いを持つ人が増えています。一方で「必要だと思うけれどまだ先」と思われている人も多いのが現状ですが、「まだ先」にはどんな思いが隠れているでしょうか。本当に先延ばしにしておいて大丈夫ですか。
終活は、決して暗いものではなく、自分や家族が安心して生きるためのもの。今日は、私がどのように終活と向き合うことになったのか、お話ししたいと思います。

私自身は、両親の介護や看取り、認知症や難病を患うお客様のサポートを経験し、その中での戸惑いや後悔、嬉しかったことやホッとしたことでの泣き笑いなどから、終活の大切さを痛感しました。
現在私は、多岐にわたる奥深い終活について、中高年の方々を中心にお伝えしたりそのサポートをしています。
終活という言葉が生まれたのは2009年。しかし、多くの人が関心を持ち始めたのはここ数年のことです。特にコロナ禍以降「終活の必要性」を感じる人が急増しました。私が終活を学び始めた2017年頃は、私の周りで【しゅうかつ】という言葉の響きは【就活】と捉えられ、【終活】の認知はほとんどありませんでした。その意識が大きく変化したのは間違いなくコロナがきっかけとなっています。
●終活の出会いと終活を伝えるご縁
25年ほど前、遠方の地方に住む義母がまだ元気だった頃のことです。「何かの時には、この箱を開けてね」そう言って見せてくれた小さな箱には、写真と新聞の切り抜きが入っていました。それは、写真屋さんで撮った義母の遺影候補の写真が2枚、そして遺族に寄り添って葬儀を執り行った葬儀社さんへのご遺族から感謝を伝えた新聞記事でした。義母が亡くなった時、この箱のお陰で家族は慌てることなく、深い悲しみにゆっくりと向き合ってお別れすることが出来ました。この時はまだ終活という発想も言葉も生まれていませんでしたが、私もこういう準備をしておきたいと思ったことが、のちに終活を始めるきっかけとなっています。
義母が亡くなって4週間後に義父も見送りました。それからずいぶん時間が経ってから、今度は車で片道1時間の所に住む実家の母の介護が始まりました。翌年には父が87歳直前で肺癌の手術、更にその翌年には夫にも腎臓癌が見つかります。これでは、私だけが終活したのでは意味がないと思い、家族の終活という難しい問題にも立ち向かうことになりました。
2023年9月に父を、同年12月に母を看取ります。紆余曲折しながら本当に怒涛の日々でしたが、両親を見送った時は、義父母を見送った時の深い悲しみや寂しさではなく、重かった肩の荷が下りてホッとした感覚の方が強かったですね。
終活を一緒にしてくれたことにとても感謝しています。

コロナ禍以降、終活に対する認知度も急速に高まり、セミナー依頼や相談も急増し今に至っています。終活についてのお話をお伝えした後「終活に対するイメージが変わった」や「終活のことがよくわかったから実際に始めてみたい」とか「家族ともっと話をしようと思う」などとおっしゃっていただくと、感無量です。
たくさんのご縁をいただき、遣り甲斐を感じつつ、更に新しい学びにもつながる充実した日々です。
終活をしていたからこそ、両親との大切な時間をしっかり持つことが出来ました。そして、家族みんなが「ありがとう。お疲れ様!」と穏やかな気持ちで見送ることが出来たのです。終活は、自分が亡くなった後の準備だけではなく「今をよりよく生ききるための準備」であり、「大切な人を、事を、物を守り、思いをつなぐシナリオ作り」です。
次回は、実際に私がセミナーでお伝えしている「終活の基本」について、「何をしたらいいの」という方々に向けてわかりやすくお伝えしますので、お楽しみに!

終活えんとらすと
山口聖子さん
- 終活サポート「終活えんとらすと」代表として、中高年向けの終活支援を行う。
- 両親の介護・看取りや、認知症・難病の方々のサポートを経験し、終活の大切さを実感。
- セミナーや相談を通じて「今をよりよく生きる終活」を伝え、実践をサポートしている。