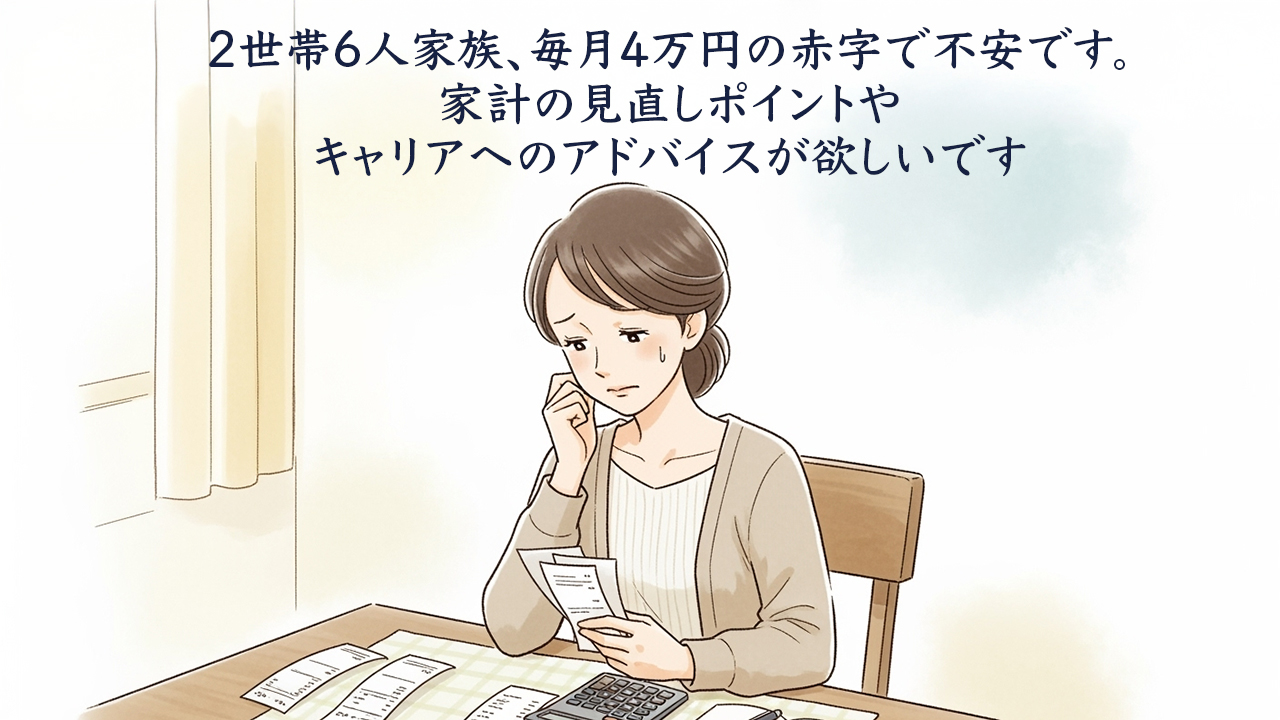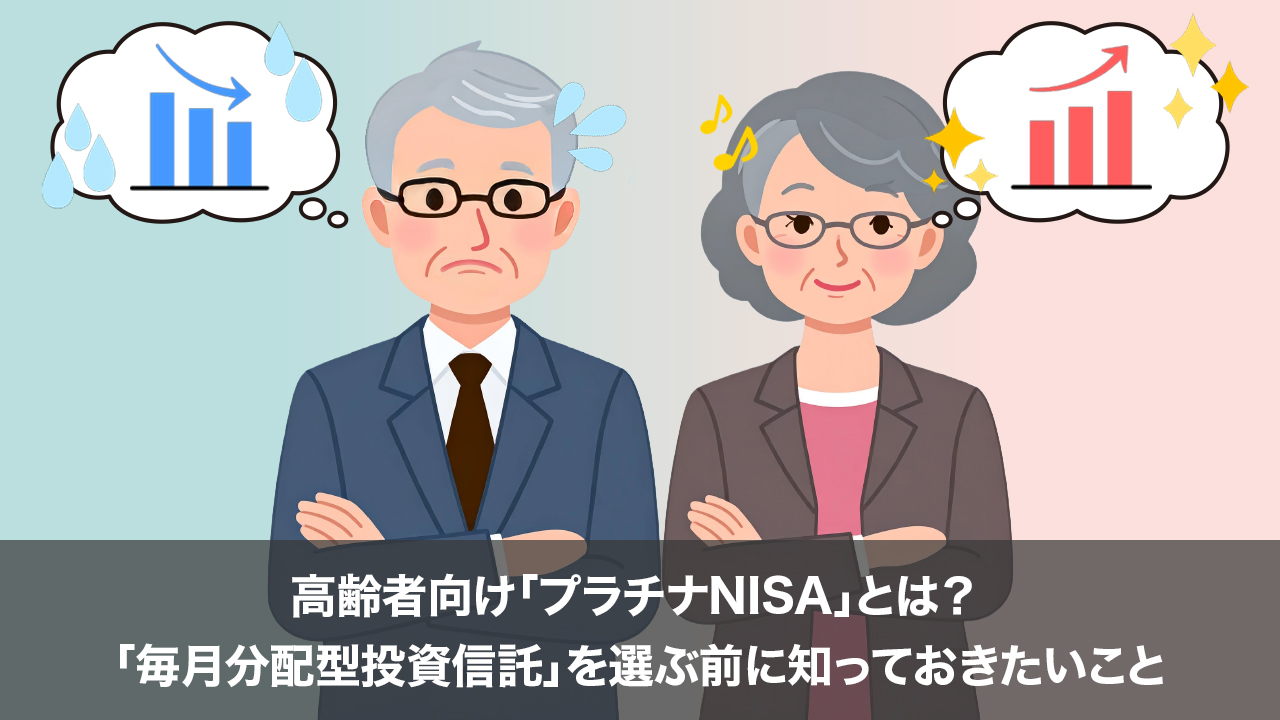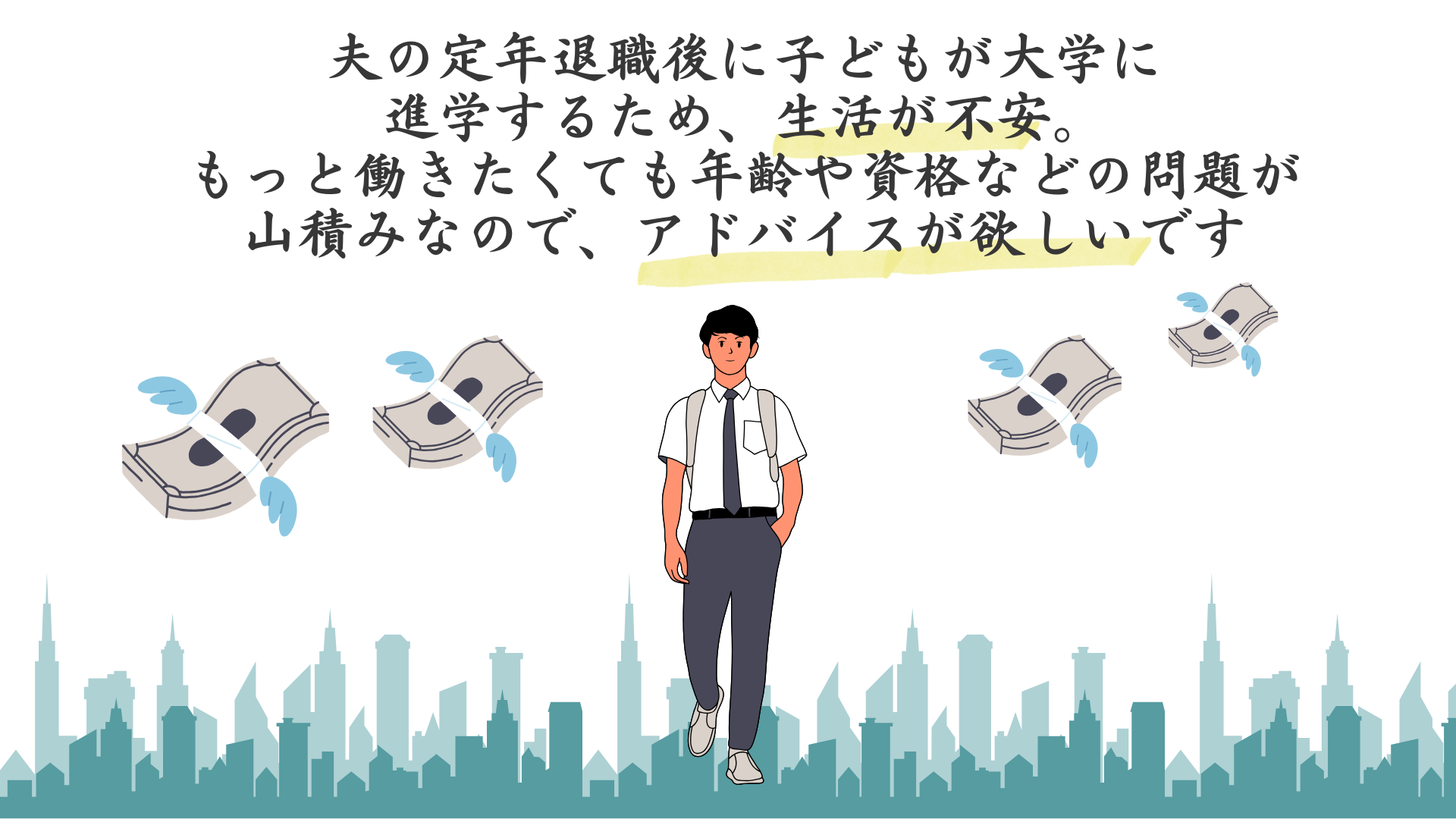
<相談内容>
「夫の定年退職後に子どもが大学に進学するため、生活していけるのか不安です。私の収入を増やしたいですが、年齢やすぐに仕事につながる資格がないこと、発達障害の子どもがいることで働き方に悩んでいます。パートの時間を増やすのか、在宅でできる仕事をするのか…無理なく現実的な方法が知りたいです」
<相談者のプロフィール>
・相談者46歳(パート勤務(事務))
-22歳で金融機関に就職、32歳で結婚・転居により退職、46歳から現職
・夫56歳(会社員)
・長男14歳(中2)
・長女9歳(小3)
<1ヶ月の収支内訳>
<収入>
・年収:夫700万円(うちボーナス160万円)、妻50万円
・1ヶ月の手取り合計:44万円(夫40万円、妻4万円)
<支出>
住居費:17万円
食費・日用品費:8万円
水道光熱費:3万2,000円
通信費:2万円
保険料:7万円
教育費・子ども費:3万円
交際費:日頃はほぼなし
娯楽費:1万円
医療費:5,000円
夫婦のお小遣い:2万4,000円
支出合計:約44万1,000円
<資産額>
夫 約1,500万円(普通預金250万円程度、残りは株式)
妻 約800万円(現金40万円、株式230万円、iDeCo25万円、投資信託140万円、普通預金365万円)
ファイナンシャルプランナーからのアドバイス

・今後の生活を優先した資金計画を立てましょう
・定年退職後、再雇用となった時のシミュレーションをしておきましょう
・大学進学資金には上限を設けることが大切です
再雇用になった時のシミュレーションをしておきましょう
ご主人の定年退職後にお子さんが大学進学を迎え、生活が心配とのこと。まずは、今後の生活を優先した資金計画を立て、そのうえで、無理のない範囲で大学進学資金を準備しましょう。
今後の生活については、「夫が定年退職後、再雇用となった時の収入が見えない」という不安が大きいようです。再雇用によって収入そのものが縮小すれば、当然、現在の生活水準を維持するのは難しくなります。
相談者自身が収入を増やすことも重要ですが、それに加えて、子どもが大学に進学した際には、アルバイトをして学校生活に必要な費用を自分で賄ってもらうことも必要かもしれません。たとえば、再雇用によって収入が現在の6割程度に減少した場合をシミュレーションし、不足する金額やその補てん方法を今から検討しておくといいでしょう。
大学進学資金には上限を設けましょう
お話によると、2人のお子さんに学資保険をかけ、それぞれ200万円受け取れるように準備なさっているということ。また、進学先は自宅から通える国公立のみと決めているそうです。ここまでしっかり決めているなら、あとは自分たちが出せる学費の上限を決め、大学入学までにどのように準備していくか、年間いくら貯めるかを考えていきましょう。
ちなみに、文部科学省の「国公私立大学の授業料等の推移」によると、国立大学の入学金は28万2,000円、4年間の授業料は214万3,200円(53万5,800円×4年間)で合計242万5,200円が標準額です。
ただし、理系の場合は大学院まで進学するかもしれませんし、国公立に受からず私立に進学する可能性もあります。それらの進路も踏まえたうえで、自分たちはいくら学費を用意するのか上限額を決めましょう。
学費が生活を圧迫する可能性は低いと言えます
親が出せる大学進学資金については、早いうちからお子さんに伝えておくことも重要です。場合によっては、大学進学後に奨学金を借りる、子どもがアルバイトをして補う、もしくは希望の進路を変更することも必要だからです。それに、あらかじめ大学の費用について話し合うことで、子どもが自分の進路を早い段階から意識するという効果もあります。
今回の相談者の場合、国公立大学への進学を検討しており、1人あたり200万円が用意できること、さらに、不足分についても補てんの目途が立っているとのことから、大きな不足の発生や、学費が生活を圧迫する可能性などは低いでしょう。
まずは再雇用後のシミュレーションを行い、将来の大まかな収支を把握したうえで、対応策を考えてみましょう。
キャリアコンサルタントからのアドバイス

- 無理なく現実的に収入を上げる働き方や方法について、一緒に考えてみましょう。
パートの時間を増やす
パートの時間を少し増やすだけでも収入は上がります。たとえば、週に5時間追加すると、月に約20時間の労働時間増加になり、その分収入が増えます。勤務先にシフトの調整を相談する、家族に家事の協力をお願いするなどして、仕事時間を確保できそうか検討してみてください。
また、正規雇用を目指すのであれば、勤務先で正規雇用に転換できるか相談してみましょう。収入が安定して、家計を支える力が一気に向上します。
収入に直結する資格を目指す
たとえば、介護福祉士や保育士など、需要の高い資格取得で就職チャンスが広がります。通信教育やオンライン講座なら、家事や育児と両立しながら学べます。ほかにも、自治体や職業訓練校の講座があります。情報を集め、ご自身に合うものを選ぶとよいでしょう。
在宅ワークを始める
事務職で培ったスキルを生かした、データ入力やライティング、バックオフィス業務など、さまざまな仕事が在宅で可能です。まずは、隙間時間を活用して小さな仕事から始めてみて、収入源の一つになるように、時間をかけて育てていくのもおすすめです。