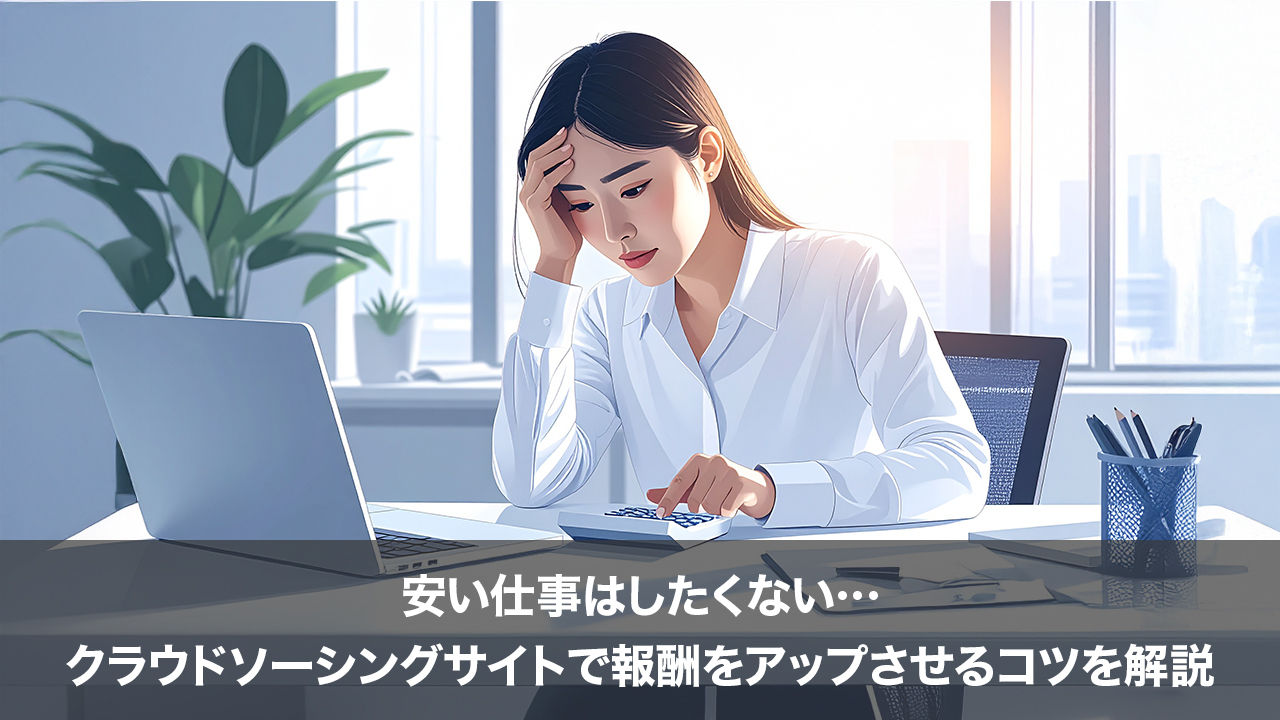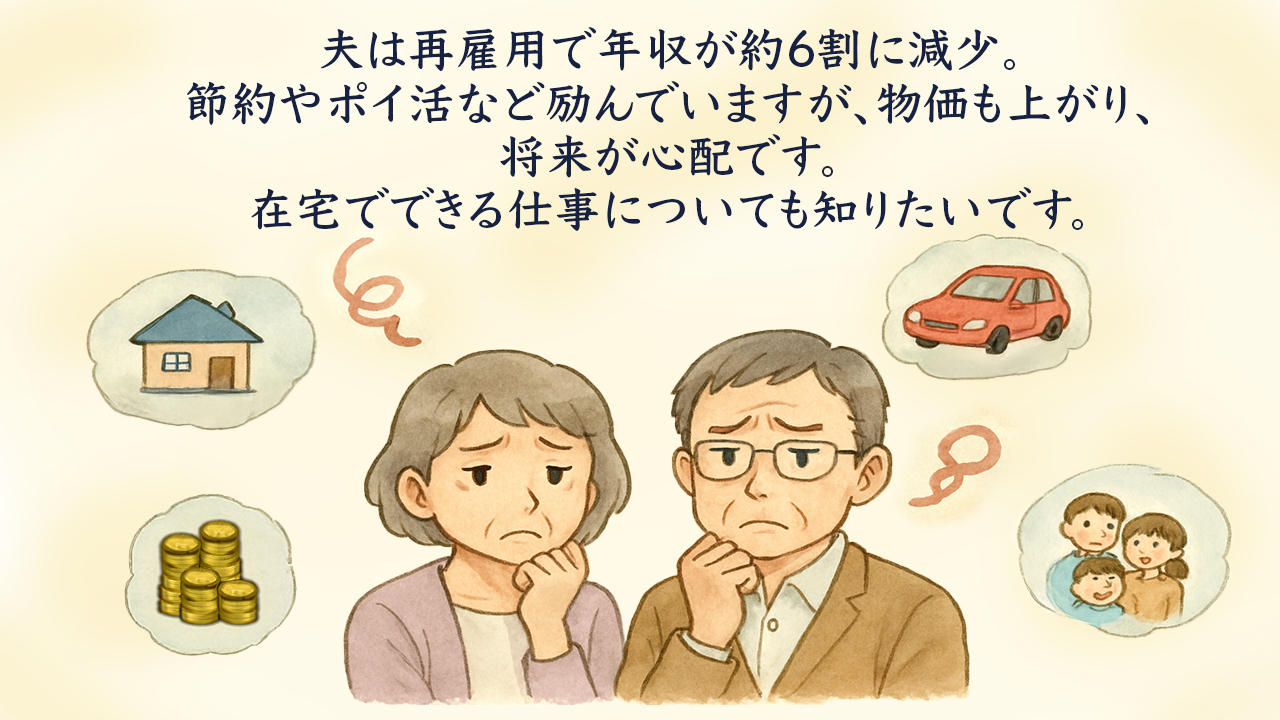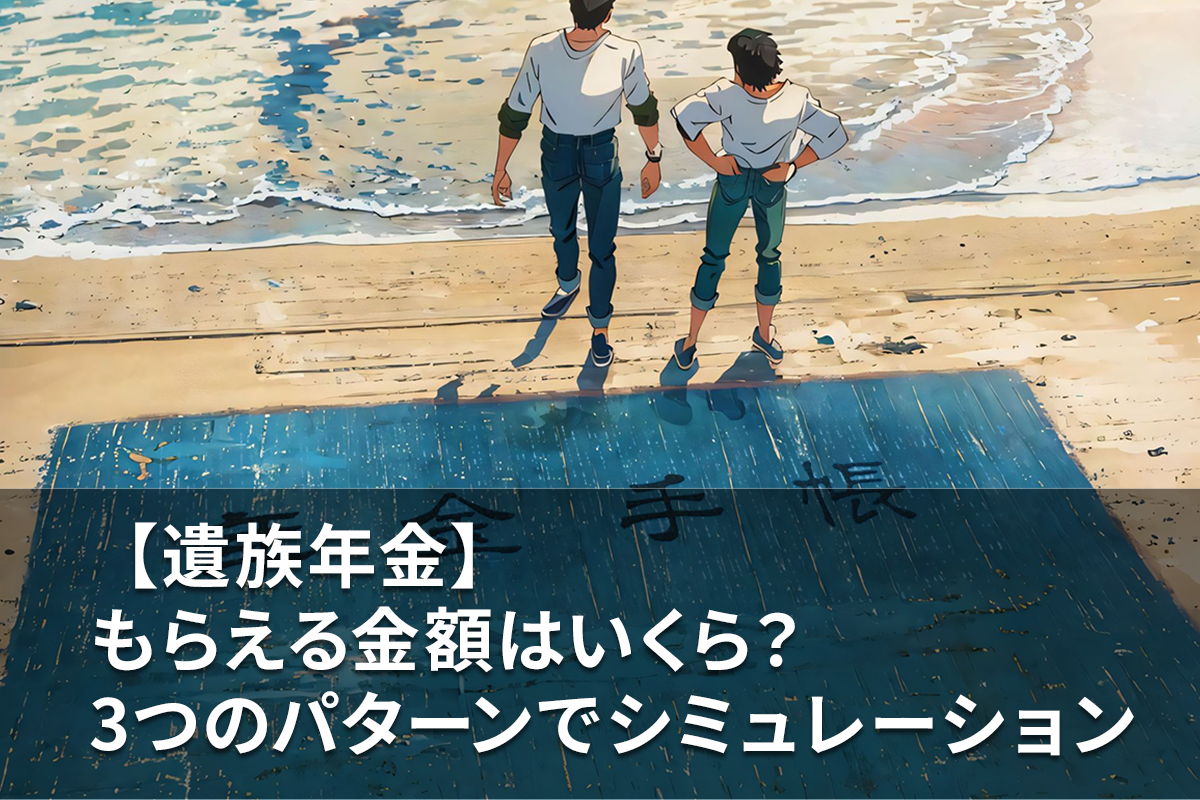
この記事でわかること
- 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある
- 夫が亡くなった場合、妻の老齢厚生年金の受給状況により、遺族厚生年金の支給額も変わる
- 妻の老齢厚生年金が夫の老齢厚生年金と同額または多い場合、遺族厚生年金は支給されない
目次
- 遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類
- 「遺族厚生年金」はいくら?3つのパターンでシミュレーション
- パターン①:妻の老齢厚生年金が年間0円
- パターン②:妻の老齢厚生年金が年間40万円
- パターン③:妻の老齢厚生年金が年間80円
- 正確な遺族年金の額を知るには年金事務所に確認を
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類
遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった時、残された家族に支給される年金です。亡くなった方が国民年金の被保険者だった場合は「遺族基礎年金」が、厚生年金だった場合は「遺族厚生年金」が支払われます。 遺族基礎年金と遺族厚生年金は、それぞれ支給される条件が異なりますが、遺族厚生年金の対象になる人が遺族基礎年金の受給要件も満たしていれば、両方の年金が受け取れます。 遺族年金の詳しい内容や計算方法などは下記のページで詳しく解説しています。遺族基礎年金や遺族厚生年金の目安がすぐにわかる「早見表」や「シミュレーションツール」も掲載していますので、そちらもあわせてご利用ください。 (参考:遺族年金は配偶者にいくら支払われる?シミュレーションと早見表で年金額を確認)「遺族厚生年金」はいくら?3つのパターンでシミュレーション
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がありますが、そのうち遺族基礎年金は、子どものいる配偶者が受け取る場合は「79万5,000円+子の加算額」、子どもが受け取る場合は「79万5,000円+2人目以降の子の加算額」で計算します。 このように、遺族基礎年金は子どもの人数で金額が決まるため、遺族厚生年金と比べると受取額を割り出す計算はさほど複雑ではありません。一方、遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の「報酬比例部分」から計算する必要があるなど、自分で正確な金額を計算するには難しい仕組みになっています。正確な金額を知りたい場合は、年金事務所や街角の年金相談センターへの問い合わせが必要です。 自分で計算したいという場合、以下の計算式を用いて報酬比例部分を求めます。<報酬比例部分の計算式>
報酬比例部分=A(平均標準報酬月額)+B(平均標準報酬額)
また、老齢厚生年金(老齢共済年金)の受給資格がある場合、下記の1と2を比較し金額の高い方が遺族厚生年金の額となります。
- A:平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの加入期間(月数)
- B:平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入期間(月数)
- 1.亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額
- 2.「上記1の額の2/3」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金の額の1/2」を合計した額
<想定する夫婦のプロフィール>
- 夫、妻ともに65歳から老齢年金を受給している
- 老齢厚生年金90万円を受給している夫が亡くなった
- 妻の老齢基礎年金は78万円
- 妻の老齢厚生年金が①年間0円、②年間40万円、③年間80万円のパターンで比較
パターン①:妻の老齢厚生年金が年間0円
妻が老齢厚生年金を受け取っていない場合、夫が亡くなった時に受け取れる遺族年金は「妻の老齢基礎年金+夫の老齢厚生年金の3/4」で計算します。 90万円(夫の老齢厚生年金)×3/4=67万5,000円(遺族厚生年金) 78万円(妻の老齢基礎年金)+67万5,000円(遺族厚生年金)=145万5,000円 この場合、妻がもらえる年間の年金支給額は、遺族厚生年金分の67万5,000円が加算されて145万5,000円になります。パターン②:妻の老齢厚生年金が年間40万円
65歳以上で老齢厚生年金を受け取れる人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る場合は、先ほどもあったように、下記1と2を比べて金額の高い方が「計算上の遺族厚生年金」の額となります。- 1.亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4の額
- 2.「上記1の額の2/3」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金の額の1/2」を合計した額
パターン③:妻の老齢厚生年金が年間80円
次に、妻の老齢厚生年金が年間80万円の場合で計算してみましょう。 1.90万円(夫の老齢厚生年金)×3/4=67万5,000円 2.90万円(夫の老齢厚生年金)×1/2+80万円(妻の老齢厚生年金)×1/2=85万円 つまり、計算上の遺族厚生年金は金額が高い方の「2」となります。次に、実際にもらえる遺族厚生年金を計算してみます。 85万円(計算上の遺族厚生年金)-80万円(妻の老齢厚生年金)=5万円 78万円(妻の老齢基礎年金)+80万円(妻の老齢厚生年金)+5万円(遺族厚生年金)=163万円(妻が受け取れる年金の合計額) この場合、計算上の遺族厚生年金と妻の老齢厚生年金の差額分5万円が加算されます。なお、妻の老齢厚生年金が夫の老齢厚生年金と同額、または多い場合、遺族厚生年金は支給されないことになります。正確な遺族年金の額を知るには年金事務所に確認を